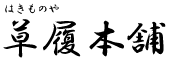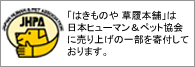成人式や大学の卒業式では足袋や雪駄はどうしたらいいですか?
フォーマルな場で履く足袋は白足袋です。
白足袋は汚れやすいので普段履くなら色足袋でもおしゃれですが。
なお、喪服のときも白足袋ですが、地域によっては黒足袋とする所もあるようです。
履物は畳表で、慶事には白鼻緒、それ以外は黒鼻緒が一般的です。
足袋の正しい履き方はありますか?
足袋は最初に履きましょう。足袋を後で履くと着崩れしてしまいます。
まず半分程外側に折り返して履き、奥まで指先が入るように両手で手前に引っ張ります。次に折り返した部分を戻してかかとまで包み込みます。
こはぜ(止め具)は必ず下から順に留めていきます。二本あるかけ糸の外側が正しい留め位置ですので足袋のサイズを選ぶときは、必ず外側のかけ糸に掛けて選ぶようにします。
大きすぎても小さすぎても見た目・履き心地ともに良くありません。洗濯でやや縮みますので0.5ミリほど大きめを選ぶといいかもしれません。
着崩れした時の対処法を教えてください!
帯がずり上がってきた
帯の内側に親指を挟み入れ、上から下に押し下げるだけで大丈夫です。
帯の締め位置を把握していればうまく加減できるはずです。
帯が緩んできた
一度解いて締め直しましょう。その際、帯の下から腰紐がはみ出していないかも合わせてチェックしましょう。
衿が緩んで広がってきた
帯の下から、襦袢、長着の順に衿先を下に引っ張って直します。
力を入れすぎないことと、神経質に直さなくても大丈夫です。
裾が広がってきた
長襦袢、長着を直す時は、まず帯の下から左右の脇部分を真下に引き下ろします。
それから下前、上前を横方向に引いて緩みとズレを整えます。その際、帯の上下の衿部分をつまめば、同時に衿の崩れも整えられます。
食事中、特に気をつけることはありますか?
ソースの飛び跳ねや食べこぼしだけでなく、袖にも十分な注意が必要です。手を動かした際に、袖口をひっかけてしまったり、料理を袂で撫でてしまうことが多いようです。これらを帽子するためには、伸ばす方の手の袂を反対の手で押さえるようにします。
食べこぼし予防には、ナプキンなどを膝の上に広げてかけておきましょう。
階段をスマートに歩くにはどうしたらいいですか?
慣れていないうちは階段の昇り降りも大変ですよね。
姿勢を正し、右手で膝の上あたりの上前を軽く持ち上げ、身体も右に向けるとスマートかつスピーディーに歩けます。
着崩れを起こして裾が広がった状態での昇り降りは危険です。十分気をつけましょう。
トイレはどうしたらいいですか?
和装の時は、大小に関わらず個室トイレを使用しましょう。
着物の裾を捲り上げて用を足す際、着物を汚さないように注意が必要です。
まず、長着と長襦袢の両方をしっかりと捲り上げて、着物の端を帯に挟むか、両脇でしっかりおさえて用を足すようにします。
洋式トイレの方が和式よりも楽ですが、クリップや洗濯バサミなどを持っていると、羽織や着物を止められて便利でしょう。
着物を汚してしまった!すぐできる対処法はありますか?
汚れ・しみがついたら、なるべく早く適切な処理を施すことが肝心です。
液体類をこぼした時は、乾いたハンカチやタオルなどで水分だけそっと拭き取ります。後はシミ取りの専門家に任せましょう。
水やベンジンで拭くとかえってシミを広げてしまうこともあるので要注意です。
車に乗るときに注意することはありますか?
タクシーなどに乗るときは少し後ろ向きになり、まずお尻から乗り込み、身体をクルッと回して足を入れます。
着物や羽織の裾がドアに挟まれないように気をつけましょう。